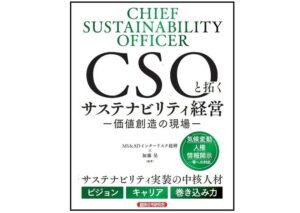SASBとは?|基準・スタンダードの概要とサステナビリティとの関わりを徹底解説
近年、企業経営において「サステナビリティ(持続可能性)」の重要性が急速に高まっています。気候変動、人権問題、社会的不平等といった課題は、企業にとって無視できないリスクであり、同時に新しいビジネス機会を生み出す要因でもあります。そのため、多くの企業が「サステナビリティ報告」や「非財務情報開示」を通じて、ステークホルダーに対する透明性を高める努力を進めています。
その際に注目されているのが「SASB(サステナビリティ会計基準審議会:Sustainability Accounting Standards Board)」です。SASBは、産業ごとに「財務的に重要なサステナビリティ課題」を明確化し、それを企業が開示するための基準を定めています。つまり、サステナビリティと企業の財務的パフォーマンスを結びつけ、投資家が比較可能な情報を得られる仕組みを提供しているのです。
本記事では、SASBの基本的な概要から、仕組みと特徴、サステナビリティとの関係、実企業が導入する際のメリットまでをわかりやすく解説します。
——————————————————————————-
1. SASBとは?
SASB(Sustainability Accounting Standards Board)は、2011年に米国で設立された独立非営利団体です。目的は、投資家が企業のサステナビリティに関連するリスクや機会を適切に評価できるようにするための会計基準の策定です。
従来、企業のサステナビリティ報告は任意であり、各社が独自の基準で情報を開示していました。その結果、投資家は企業間の比較が難しく、また財務的に重要な課題が十分に明確化されないという問題がありました。SASBはこの課題に対応し、「投資家にとって重要な非財務情報を標準化する」ことを目指しました。
2022年にはSASBはIFRS財団に統合され、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会:International Sustainability Standards Board)の一部となりました。現在、ISSB基準(IFRS S1、S2)が国際的に採用されつつありますが、その基盤にはSASBスタンダードが活用されています。つまり、SASBは今後の国際的な非財務情報開示の中核的役割を担う存在となっています。
——————————————————————————-
2. SASBスタンダードとは?
SASBスタンダードの最大の特徴は、77の産業別に基準を定めている点です。例えば、製造業では労働安全や環境負荷が重視されますが、金融業ではデータセキュリティや貸出ポートフォリオの気候リスクが注目されます。
SASBはこうした産業ごとの差異を踏まえ、それぞれの産業で投資家にとって「財務的に重要」なサステナビリティ課題を特定し、開示指標を示しています。
例えば、製造業の一分野では以下のような指標が含まれています。
- 温室効果ガス(GHG)排出量
- エネルギー効率の改善率
- 労働災害の発生件数
- 製品ライフサイクルにおける環境影響
一方、金融サービスでは次のような項目が挙げられます。
- 融資先における気候関連リスクの評価手法
- データ漏えいの件数
- 顧客に対する金融リテラシー向上施策
このように、SASBスタンダードは「一律の項目」ではなく、各産業において投資家が重視する情報を選定している点に特徴があります。
投資家にとってSASBスタンダードは、比較可能で、財務的に重要な非財務情報を得られる点で価値があります。従来のCSR報告書やサステナビリティ報告書は、内容が多様で比較しづらいものでした。しかしSASBスタンダードを活用することで、企業間での横比較や業界全体のリスク評価が可能になります。
——————————————————————————-
3. SASBとサステナビリティの関わり
SASBの特徴は、サステナビリティ課題を「社会的・環境的な意義」にとどめず、企業の財務的影響と結びつける点です。
- ESGやSDGsは、社会的な便益や持続可能性全般を強調します。
- 一方SASBは、「その課題が企業の収益やコスト、資産評価にどう影響するか」という観点で整理されています。
つまり、サステナビリティを「企業価値創造の要素」として捉えるフレームワークがSASBです。このアプローチにより、企業は単なる社会的責任ではなく、長期的な成長戦略の一環としてサステナビリティ課題に対応する必要性が明確化されます。
——————————————————————————-
4. SASBを活用するメリットと課題
メリット
- 投資家に対する透明性の向上
国際的に認知された基準に沿って開示することで、投資家からの信頼を獲得できます。 - 産業ごとに特化した指標
自社に関連のない情報ではなく、業界に適した課題にフォーカスできるため、効果的な情報開示が可能です。 - グローバル基準との親和性
ISSB基準やTCFDなど、他の国際基準との整合性をとりやすくなります。
課題
- 日本企業での導入事例はまだ限定的
欧米に比べ、国内での認知度は低く、事例も少ないのが現状です。 - 他基準との併用が必要
GRIやTCFD、CDPなど、複数の基準との整合性を考慮する必要があり、実務負担が増える可能性があります。 - 社内体制の整備が不可欠
財務部門とサステナビリティ部門の連携が求められるため、社内体制の見直しが必要です。
——————————————————————————-
5. SASBと他のサステナビリティ基準の比較
- GRI:ステークホルダー全体に向けた包括的な報告。社会・環境への幅広い影響にフォーカス。
- SASB:投資家重視。財務的に重要な課題にフォーカス。
- TCFD:気候関連リスクに特化。シナリオ分析を求める点が特徴。
- ISSB基準:SASBを基盤としつつ、国際的に統合された基準として展開。
このようにSASBは「投資家目線」の開示を重視し、他の基準と補完関係を持ちながら国際的な開示基盤を形成しています。
——————————————————————————-
6. 日本企業におけるSASB対応の動向
日本でも非財務情報開示の重要性は急速に高まっています。金融庁は有価証券報告書でのサステナビリティ情報開示を強化し、東京証券取引所も上場企業に対して気候関連開示を求めています。
一部の大手企業は、すでにSASBスタンダードを参考に開示を始めています。今後はISSB基準が国際的に普及するにつれ、日本企業にもSASBの情報開示が求められる可能性があることでしょう。
——————————————————————————-
7. SASB導入における課題と解決策
しかし実際にSASBに取り組む立場になると、次のような悩みに直面しがちです。
- 専門的な知識やリソースの不足
- 膨大なデータ収集・管理の難しさ
- 他のフレームワークとの整合性の確保
こうした課題を克服するために、外部の専門家やコンサルティング会社の支援を受けることが効果的です。特にマテリアリティ特定や国際基準の最新動向を踏まえたアドバイスは、社内だけで対応するには限界があります。
——————————————————————————-
8. 専門家のサポートが必要な理由
SASBをはじめとするサステナビリティ開示は専門的な知識が必要であり、自社だけで完結するのは困難です。特にさまざまな国際基準の理解や報告書の作成には時間とコストがかかります。
そのため、多くの企業が外部の専門家やコンサルティング会社の支援を受けながら開示体制を整備しています。外部のコンサルティングサービスを活用することで、効率的かつ正確に対応することができます。
👉 LOCAL STARのサステナビリティ支援サービスでは、豊富な知見と最新動向を踏まえたSASBをはじめとする非財務情報開示やサステナビリティ経営に関する支援を提供しています。
専門家とともに、自社に最適なSASBをはじめとする非財務情報開示の仕組みを整えてみませんか?
👉 詳しくはこちらをご覧ください: LOCAL STARのサステナビリティ支援サービス

——————————————————————————-
8. まとめ
SASBとは、投資家が重視する非財務情報を産業別に標準化するために設立された国際的基準を提供しています。その内容は、77の産業別スタンダードを持ち、財務的に重要なサステナビリティ課題にフォーカスしています。SASBはISSB基準の基盤となっており、今後ますます重要性が高まっていくでしょう。
SASBを活用することで、国際基準に沿った情報開示を進めることで、投資家からの信頼を獲得し、企業価値を高めることにつながります。ただし、導入には専門的な知識と体制が必要となるため、外部コンサルティングの活用も有効です。
持続可能な企業経営を実現する第一歩として、SASBへの対応を進めてみてはいかがでしょうか。
——————————————————————————-
📌 まずはここから始めましょう
👉 LOCAL STARのサステナビリティコンサルティングを見る

——————————————————————————–