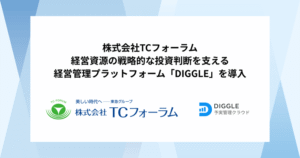非財務情報開示とは?基準・重要性・進め方を徹底解説
近年、企業に求められる情報開示は大きく変化しています。従来は「売上高」「利益率」といった財務情報が重視されていましたが、今ではそれに加えて非財務情報が注目されています。非財務情報とは、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)など、いわゆるESGに関する情報を中心とした、企業の持続可能性や将来の成長可能性を示すものです。
特に投資家や金融機関、取引先は、企業の長期的な価値を見極めるために非財務情報を重視するようになっています。そのため、上場企業だけでなく、中小企業やスタートアップにとっても「非財務情報をどのように開示するか」は避けて通れない課題となっています。
この記事では、非財務情報開示の意味や背景、基準、具体的な進め方を詳しく解説し、最後に企業がどのように取り組むべきかをまとめます。
——————————————————————————–
1. 非財務情報開示とは?
非財務情報とは、財務数値以外で企業価値に影響を与える情報を指します。つまり、非財務情報の開示は、単なる「CSR活動の紹介」ではなく、企業の価値を正しく伝える経営戦略の一部として重要性を増しています。
財務情報との違い
- 財務情報:売上、利益、キャッシュフロー、資産など、定量的で過去の実績を示すもの。
- 非財務情報:企業の将来に影響を与える可能性のある要素。定性的な内容も多く、持続可能性に関わる。
このように財務情報は「過去の業績」を中心に示しますが、非財務情報は、企業が持続的に成長できるかどうかを測る重要な指標であり、長期的な投資判断に大きな影響を与えています。
——————————————————————————–
2. 非財務情報開示の重要性
非財務情報がなぜ重要なのかを理解するには、投資家・社会・企業それぞれの視点から考える必要があります。
- 投資家からの要請
機関投資家やESG投資家は、企業の持続可能性を投資判断に組み込んでいます。財務データだけでは「将来リスク」を評価できないため、非財務情報が必要となります。非財務情報を開示していない企業は、投資対象から外されるリスクもあります。 - 顧客・取引先からの信頼
取引先企業もサプライチェーン全体でのESG対応を重視するようになり、非財務情報を公開することが信頼獲得につながります。中小企業であっても非財務情報を開示できていないと取引機会を失う可能性があります。 - 規制強化
世界的に非財務情報開示の義務化が進んでいます。欧州ではCSRD(企業サステナビリティ報告指令)が導入され、日本でも有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示が求められるようになっています。 - 企業の持続的成長
非財務情報の開示は、単なる外部への報告義務ではなく、企業の長期的な競争力やブランド価値を高めることにつながります。
——————————————————————————–
3. 非財務情報開示の国際的な基準
非財務情報の開示には国際的な基準が複数存在します。代表的なものを紹介します。
- TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース):G20財務大臣および中央銀行総裁からの要請で金融安定理事会が公表。気候変動に関する開示項目を設定。多くの国・企業が賛同しています。
- GRI(Global Reporting Initiative):NPO:Global Reporting Initiativeが公表。世界の大手企業の上位250社のうち、75%が利用していると言われる持続可能性に関する包括的な情報開示基準。
- SASB(Sustainability Accounting Standards Board):米国向けの非財務情報開示基準であり、米サステナビリティ会計基準審議会が公表。業界ごとのサステナビリティ基準を設定。
- ISO規格
環境マネジメント(ISO14001)や品質マネジメント(ISO9001)など、各種の国際規格が非財務情報開示と関連しています。 - ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)
IFRS財団が設立した新しい基準策定機関で、2023年6月に「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項(IFRS S1号)」及び「気候関連開示(IFRS S2号)」の2つを公表。
すべての基準に対応するのは難しいため、自社に関連性の高いものから取り組むことをおススメします。
——————————————————————————–
4. 非財務情報開示のメリットとリスク
メリット
- 投資家や格付機関からの評価向上と信頼獲得
- 取引先との関係強化
- 採用におけるブランド力向上により、優秀な人材の採用や定着につながる
リスク(開示しない場合)
- 投資機会を逃す
- サプライチェーンから外される可能性
- 消費者や社会からの信頼低下
——————————————————————————–
5. 非財務情報開示の取り組むべきステップ
- 体制の構築
サステナビリティの知識を深め、自社に最適な推進体制の構築 - マテリアリティ(重要課題)の特定
自社にとって重要な課題を抽出。 - データ収集・定量化
現状把握とともに、環境負荷や人的資本データを集める仕組みづくり。 - レポーティング
コーポレートサイト、有価証券報告書、統合報告書、サステナビリティレポートなどでの公表。 - 外部評価対応
ESG格付機関や投資家からの評価に備える。
しかし、これらを自社だけで進めるのは容易ではありません。専門的な知識や経験を持つ外部コンサルティングの活用が効果的です。
——————————————————————————–
6. 専門家のサポートが必要な理由
非財務情報開示は専門的な知識が必要であり、自社だけで完結するのは困難です。特にさまざまな国際基準の理解や報告書の作成には時間とコストがかかります。
そのため、多くの企業が外部の専門家やコンサルティング会社の支援を受けながら開示体制を整備しています。外部のコンサルティングサービスを活用することで、効率的かつ正確に対応することができます。
👉 LOCAL STARのサステナビリティ支援サービスでは、豊富な知見と最新動向を踏まえた非財務情報開示やサステナビリティ経営に関する支援を提供しています。
専門家とともに、自社に最適な非財務情報開示の仕組みを整えてみませんか?
👉 詳しくはこちらをご覧ください: LOCAL STARのサステナビリティ支援サービス

——————————————————————————–
7. まとめ
非財務情報開示は、もはや大企業だけの課題ではありません。国際的な規制強化や投資家の要請が進む中、対応を後回しにすることはリスクとなり得ます。投資家や取引先、社会からの信頼を獲得するためには、大企業だけではなく中小企業やスタートアップも積極的に取り組む必要があります。
「財務+非財務」の両輪で企業価値が随時測られている時代の中で、開示は一度に完璧に行う必要はなく、段階的に整備していくことが重要です。その際、専門家の知見を取り入れることで、効率的かつ効果的に進めることができます。
非財務情報を正しく開示し、企業価値を高める第一歩を踏み出しましょう。
——————————————————————————–
📌 まずはここから始めましょう
👉 LOCAL STARのサステナビリティコンサルティングを見る

——————————————————————————–