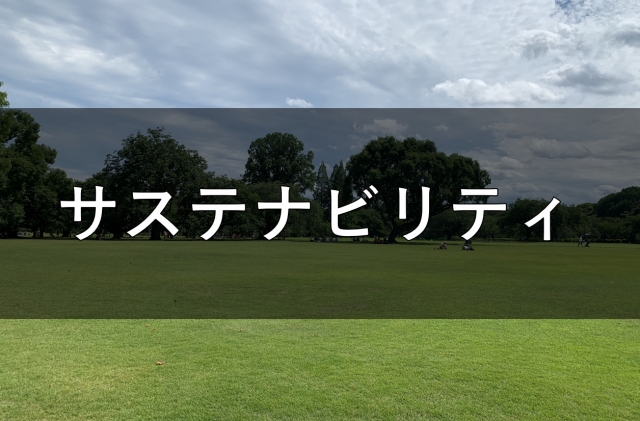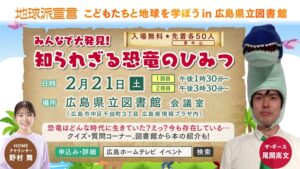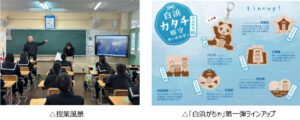サステナビリティとは?企業が取り組むべきことをわかりやすく解説
ビジネスや暮らしにおいて日常的に耳にするようになった「サステナビリティ(Sustainability)」。日本語に訳すと「持続可能性」という意味です。
さまざまな社会の課題が浮き彫りになる中、サステナビリティは一部の専門家だけの関心事ではなく、すべての人々や企業にとっての責任となりつつあります。
本記事では、サステナビリティの意味や歴史と背景、サステナビリティの重要性などをご紹介していきます。
——————————————————————————–
1.サステナビリティとは?
サステナビリティとは、環境・社会・経済の観点から世の中を持続可能にしていくという考え方のことをさします。簡単に言うと、「長く続くようにすること」を指します。
企業活動においてサステナビリティに配慮する経営を「サステナビリティ経営」と言います。
上場企業が実施することを定めている「コーポレート・ガバナンスコード」にも各企業がサステナビリティに取り組むよう記載されており、今後企業として生き残っていくためにはサステナビリティの観点が重要です。
また、世界経済フォーラム年次総会2020においても話題となった『ステークホルダー資本主義』はこのサステナビリティを進める上で重要な考え方です。『ステークホルダー資本主義』とは「企業にはすべての利害関係者に経済的利益をもたらす責任がある」という考え方であり、このステークホルダーとは取引先やパートナーだけではなく、従業員やその家族、就職希望者、業界や同業他社、金融機関、格付け機関、国や行政、地域社会や自然環境等、あらゆる関係者をさしています。これらに対し、事業活動をしながらともに利益を享受できるようにすることが企業に求められています。
なお、サステナビリティは時代によって求められる内容が変わってくるため、常にその変化を把握し対応していくことが企業に求められています。これからの企業はサステナビリティの観点を捉え、時代に合わせて「何度でも生まれ変われる会社」が生き残っていくことになるでしょう。
——————————————————————————–
2.サステナビリティの歴史と背景
「サステナビリティ」という用語が広く認知されるようになったのは、1987年に国連が発表した「われら共有の未来(ブルントラント報告)」がきっかけとされています。この報告書では、「次世代のニーズを損なうことなく、今の世代のニーズを満たす開発」と定義されています。つまり、サステナビリティとは長期的に持続可能な状態を目指すことであり、今だけでなく未来の人々の暮らしや社会、地球環境を考えながら行動することこそが、サステナビリティの本質です。しかしながら当時はまだサステナビリティという考えが大きく企業に影響を与えることはありませんでした。
その後、1990年代頃から「CSR(企業の社会的責任」という言葉が広まりました。これは「社会・環境への価値提供は財務リターンと矛盾する」という考え方です。すなわちビジネスと社会と環境は別であり、利益を減らしてでも社会貢献を果たしていくという考え方です。つまりビジネスで生み出した利益から、環境保護団体や人権保護団体などへ寄付をしていくことなどがCSR活動にあたります。この考え方で活動している企業はまだまだ多い状況になります。
一方、2010年頃から「CSV(共通価値の創造)」という言葉が広まりました。これは「社会・環境への価値提供は財務リターンと矛盾する」という考え方です。これはビジネスと関係の深い環境および社会分野の活動を生み出し実行していくという考え方です。
これがさらに進み、2015年頃から「サステナビリティ」という言葉がじわじわと広まってきました。前述のとおり、サステナビリティとは、環境・社会・経済の観点から世の中を持続可能にしていくという考え方のことをさします。そもそもビジネスは環境・社会の中で活動しているものなので、環境・社会に投資することはビジネスにとっても有益だという考え方になります。多くのグローバル企業はこの考え方で動いており、グローバルスタンダードになっています。
——————————————————————————–
3.サステナビリティの重要性
(1)消費者の価値観の変化
特にZ世代やミレニアル世代の間では、商品やサービスの価格・機能だけでなく、「その企業が社会や環境にどう向き合っているか」が購買行動に大きな影響を与えています。
(2)投資の潮流:ESG投資
2005年に国際連合がPRI(責任投資原則)を定めました。PRIをとても簡単に要約すると、投資家に対し、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)に力を入れている企業に投資(ESG投資)をし、力を入れていない企業からは資金を拠出しないよう求める投資の原則です。日本の多くの投資家もこれに署名を行い実施しています。
(3)サプライチェーンマネジメント(SCM)の概念の広がり
そしてサステナビリティはサプライチェーン全体で行うよう国際的に求められています。サプライチェーンとは原料の調達先・製造先・輸送先・販売先等、商品に関わる全体のことをさします。多くのグローバル企業や大手企業は「こういった企業と取引をします」という調達方針を示し、それを実行できている企業と取引を行います。また、それを実施しているか取引先をチェックする企業が急激に増えています。
(4)法規制対応による競争優位性の確保
世界各国にて、サステナビリティに関する国際規格や法規制が次々に発表され、年々厳しさを増しています。サステナビリティ経営を実践することで、さまざまな罰金・制裁などのイレギュラーなコスト負担を回避し、企業の信頼性を高めることができます。
つまり、もはやサステナビリティを重視した経営をしなければ投資も得られず、仕事を貰えるということもなくなってくることを意味しています。これからのビジネスはサステナビリティが経営の中心であり、この世界の潮流を読まずして、ビジネスが続いていくことは今後難しくなっていくことでしょう。
——————————————————————————–
4. サステナビリティ推進における課題
多くの企業がサステナビリティ推進において、以下のような悩みに直面しています。
•「サステナビリティにも取り組みたいけど、一体何から始めたら良いの?」
•「取り組んではいるけれども、なかなか具体的に進められていない」
こうした課題に対して、第三者の視点からサポートする外部の支援サービスを活用する企業が増えています。
——————————————————————————–
5. 専門家の力を活用し、実効性ある施策を【外部サービスの紹介】
サステナビリティ推進には、多岐に渡る知識と経験、専門的なノウハウが必要です。社内のリソースや知見だけでは対応が難しい場面が多く、信頼できる外部パートナーと組むことが、推進において重要なポイントとなります。
そこでおすすめしたいのが、企業のサステナビリティ活動を総合的に支援する

本サービスは、サステナビリティに精通した専門家の伴走支援により、貴社のサステナビリティ推進を強力にサポートするサービスです。
サステナビリティ推進に向けた第一歩を、専門家とともに踏み出してみてはいかがでしょうか。
——————————————————————————–
📌 まずはここから始めましょう
👉 LOCAL STARのサステナビリティコンサルティングを見る

——————————————————————————–