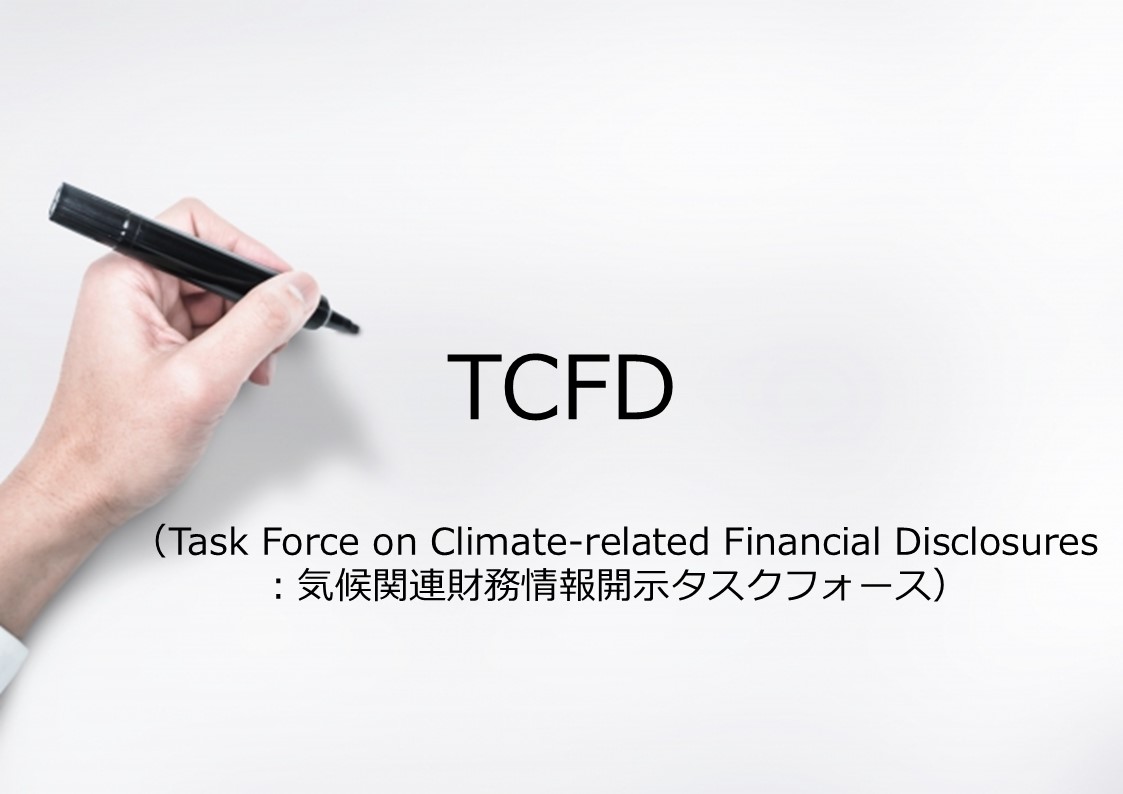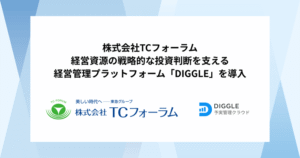TCFDとは?企業が知っておくべき気候関連財務情報開示の重要性を解説
近年、気候変動はもはや環境問題にとどまらず、企業経営そのものに大きな影響を与えるリスク要因となっています。異常気象や自然災害によるサプライチェーンの寸断、炭素価格や規制強化によるコスト増、低炭素社会に向けた産業構造の変化など、企業を取り巻く外部環境は急速に変化しています。
こうした状況のなかで、投資家や金融機関は、従来の財務情報だけでなく、気候変動に対する企業の対応力やリスクマネジメントを重視するようになりました。その流れを受けて登場したのが「TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)」です。
この記事では、TCFDの基本的な概要から、企業にとっての重要性、実際の開示内容やメリット、さらに日本企業の動向や実務対応のステップまでをわかりやすく解説します。
——————————————————————————-
1. TCFDとは何か?
「TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」は、2015年に当時のG20からの要請を受けて、金融安定理事会(FSB)が設立した国際的なイニシアチブです。世界的な金融危機の再発防止を目的として活動していたFSBが、気候変動リスクが金融市場全体に重大な影響を与える可能性があることを踏まえ、企業に対して気候変動に関する情報開示を求めるために設立しました。
TCFDの目的は、企業が気候関連の「リスク」と「機会」を適切に開示することで、投資家や金融機関がより正確に企業価値を評価できるようにすることです。つまり、気候変動対応を単なるCSRや環境活動としてではなく、経営・財務情報として投資判断に直結する情報として扱うことを求めています。
その結果、世界中の投資家・金融機関がTCFD提言を重視するようになり、企業にとっては対応が避けられない流れとなりました。
日本国内においては、TCFD 提言へ賛同する企業や金融機関等が一体となって取組を推
進するための組織「TCFDコンソーシアム」が設立され、多くの企業や金融機関が参加しています。特に日本は世界的にもTCFDへの賛同表明企業数が多く、国内でも注目度が高い状況です。。
——————————————————————————-
2. なぜTCFDが重要なのか?
TCFDが注目される背景には、以下のような要因があります。
- 投資家の期待の変化
投資家や機関投資家は、企業の持続的な成長性を評価する際、従来の財務データだけでは不十分だと考えるようになっています。特に気候変動リスクは、長期的な企業価値を大きく左右するため、開示の透明性が求められています。 - 規制・政策の強化
日本を含む各国政府は、2050年カーボンニュートラルを目指して政策を加速させています。排出規制や炭素税などの導入が企業に与える影響は無視できません。 - 市場の潮流
東証プライム市場の上場企業には、TCFDやそれに準じた情報開示が事実上求められています。すでに多くの大手企業がTCFD提言に基づいた開示を行っており、対応しない企業は投資家からの評価を下げるリスクを負うことになります。 - サプライチェーンの要請
大企業のサプライチェーンに属する企業は、取引先からの要請で対応を迫られるケースが増えており、取引継続や拡大の観点からも無視できません。
このように、TCFDは単なる「国際的な推奨」ではなく、企業の成長戦略や資本市場での評価に直結する要素となっているのです。
——————————————————————————-
3. TCFD提言の4つの柱
TCFD提言は、企業が開示すべき情報を「4つの柱」で整理しています。
| ガバナンス |
| a) 気候関連のリスクと機会についての、取締役会による監視体制 |
| b) 気候関連のリスクと機会を評価・管理する上での経営者の役割 |
| 戦略 |
| a) 組織が識別した、短期・中期・長期の気候関連のリスクと機会 |
| b) 気候関連のリスクと機会が組織のビジネス、戦略および財務計画に及ぼす影響 |
| c) 2°C 以下のシナリオを含む異なる気候関連のシナリオを考慮した、組織戦略のレジリエンス |
| リスク管理 |
| a) 当該組織が気候関連リスクを識別および評価するプロセスを説明する。 |
| b) 当該組織が気候関連リスクを管理するプロセスを説明する。 |
| c) 当該組織が気候関連リスクを識別・評価および管理するプロセスが、組織の総合的なリスク管理にどのように統合されているかを説明する。 |
| 指標と目標 |
| a) 自らの戦略とリスク管理プロセスに即して、気候関連のリスクと機会を評価するために用いる指標を開示する。 |
| b) Scope 1、Scope 2 および、当てはまる場合はScope 3 の温室効果ガス(GHG)排出量と関連リスクについて説明する。 |
| c) 気候関連リスクと機会を管理するために用いる目標、および目標に対する実績を開示する。 |
この4本柱に基づく開示を行うことで、投資家は企業の気候変動対応力を客観的に評価できるようになります。
——————————————————————————-
4. 企業にとってのメリット・導入効果
TCFDに基づく開示を行うことで、企業にはさまざまなメリットがあります。
- 投資家・金融機関からの信頼獲得
透明性の高い情報開示は、資金調達に有利に働きます。 - ESG評価の向上
ESG投資が拡大するなか、TCFD対応は格付機関や評価機関のスコア向上につながります。 - リスクマネジメントの強化
気候変動を経営リスクとして捉え、シナリオ分析を行うことで事業継続力が高まります。 - 中長期的な企業価値向上
サステナブルなビジネスモデルを構築することで、社会的評価と収益性の両立が可能になります。
——————————————————————————-
5. TCFD開示に対応するためのステップ
実際に企業がTCFD開示に対応するためには、以下のプロセスが必要です。
- 社内体制の整備(ガバナンス)
- 担当部署や経営層を巻き込んだ体制づくり。
- シナリオ分析の実施(戦略)
- 2℃シナリオや1.5℃シナリオなど、気候変動の将来シナリオに基づき事業影響を評価。
- リスク・機会の特定(リスク管理)
- 自然災害、規制強化、技術革新、市場変化などを整理。
- 指標・目標の設定(KPI・GHG排出量)
- Scope1・2・3排出量の算定と削減目標の設定。
- レポート化・ステークホルダー開示
- サステナビリティ報告書、統合報告書、ウェブサイトでの開示。
この流れは理想的ですが、実際には多くの企業が「シナリオ分析」や「リスク・機会の特定」でつまずいています。
——————————————————————————-
6. TCFD対応に専門家のサポートが必要な理由
TCFDへの対応は、専門性が高いため、多くの企業が外部の専門家やコンサルティング会社の支援を受けながらTCFD対応を実行しています。
👉 LOCAL STARのサステナビリティ支援サービスでは、豊富な知見と最新動向を踏まえたTCFDに関する支援を提供しています。
専門家が伴走し、企業の実態に即した形でTCFDを推進できるため、自社だけで進めるよりも効率的かつ高品質な開示が可能になります。
👉 詳しくはこちらをご覧ください: LOCAL STARのサステナビリティ支援サービス

——————————————————————————-
7. まとめ
TCFDは、企業にとって「義務的な対応」ではなく、投資家や社会からの信頼を獲得し、中長期的な成長を実現するための重要なフレームワークです。
ただし、実務的には専門知識が求められるため、多くの企業にとってハードルが高いのも事実です。
だからこそ、専門家の支援を得ながら効果的に対応を進めることが成功の鍵となります。
まずは専門家に相談することから始めてみませんか?
——————————————————————————-
📌 まずはここから始めましょう
👉 LOCAL STARのサステナビリティコンサルティングを見る

——————————————————————————–